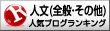「私、ウソが言えないタチでして…」とい口にする人は、たいていの場合ウソをつきます。そういう前置きは時には効果的ですが、往々にして打算を含んでいるものです。
「お世辞が言えないタチですが」の2つのタイプ
このセリフを何かにつけて口にする人には、二つのタイプがあります。
- ひとつは、本当にお世辞をいえないタイプ
- もうひとつは、ゴマスリであることを隠すために口にするタイプ
後者はタチが悪いですね。
というのは、「お世辞が言えないタチですが」といったすぐ後に、平気で相手のことを褒めまくったりするからです。
ゴマスリは、ゴマスリであることがバレないために、あらかじめ「お世辞が言えないタチ」であると断ってくるわけです。
だから、後者の場合は、「私はゴマスリです」と白状しているとしか思えないセリフですが、本人はそうは思っていない場合があるようです。
「私、ウソは大嫌いでして」と時々口にする人も、「私、時々ウソをつきます」と白状している場合が多いので要注意です。
いずれにしても、お世辞をよく口にするタイプは、処世の方便として、相手をほめてほめまくって、ゴマをするわけです。
だから、「わたしはお世辞が言えないタチでして」と断ってから、やたらとお世辞を言ってきたら、「あなた、お世辞が言えない人だったはずですよね」と、突っ込んでやると良いでしょう。
お世辞というのは不思議なもので、いわれたほうも最初は警戒しますが、何度も何度も繰り返し言われますと、だんだんと耳に心地よくなってくるものですから、気をつけないといけません。
ゴマすり人間と分かったら、油断して有頂天にならず、話半分で聞くくらいの気持ちでいるといいでしょう。
※ゴマすり部下の心理

イエスマンといわれるゴマすりの部下がいます。
彼らの言動は、実は上司に対する嫌悪感の反動である場合が多いのです。このように、評価を落とさないよう本心とは逆の態度をとるのは反動形成の一種です。
反動形成の嘘
抑圧されている欲求が実際の行動に表れないように、本来の自分の感情や思っていることと正反対の行動をとってしまうこと。
本心では嫌っている上司に対し、ゴマをすったり進んで言いなりになったりする。
「部長は僕の憧れです!」
お世辞は相手の好意を得るための迎合行動
お世辞・同意・卑下・笑顔
心理学用語に、迎合行動というものがあります。
相手の好意を得るための言動を指し、お世辞を言う、相手の意見に同意するなど、いろいろなものがあります。
例えば、「私ってバカだから」と、自分を卑下する発言。バカだというのは単なるポーズであり、自分を低く見せることで、相手を持ち上げようとする心理が働いているのです。
笑顔のない無愛想な人と話していると、「怒っているのかな」と不安になってしまいます。それを避けるための迎合行動が笑顔です。
その一方で、過剰な迎合行動が、逆に人を不愉快にさせることもあります。
見え透いたお世辞や押し付けがましい親切が、うっとうしく感じられるときは、「この人は、私の好意が得たいのだな」と考えてみましょう。「この人、迎合行動が下手くそだな…」と思えば、いらだちも収まるかもしれません。
◇迎合行動の4パターン
迎合行動には次の4パターンがあり、組み合わせて使います。
賛 辞
お世辞を言って、 相手をいい気分にさせるのは、 最もポピュラーな迎合行動。ただし、明らかにウソとわかるようなお世辞は逆効果になる。
卑 下
賛辞の逆で、自分を卑下することで、相手を持ち上げるというやり方。 自己評価
が低い場合にも、自分を卑下する行為が見られる。
同 意
相手の意見に「その通りです」と同調する。同調行動は、仲間意識を生み出すが、何度も繰り返すと、「自分の意見がない人」と思われる。
親 切
相手の行動に注意し、何かと気を配る。
※急に親切になる人がいます。何かを頼みたい下心があるか、後ろめたい気持ちがある場合が多いです。いずれにしても、あまり深入りした関係にならない方が良い人でしょう。
お世辞を使うなら上手に言おう
うまいお世辞は人間関係を円滑にする
わかりやすい社交辞令
- ×「行きたくありません」⇒〇「あいにく先約があって」
わかりやすいお世辞
- 〇「ナイスショット!」
社交辞令やお世辞は、人に気に入ってもらうための迎合行動の一種で、厳密にはウソです。
相手に屈するような印象もありますが、たとえその場限りの嘘だとわかっていても、相手を喜ばせ、人間関係を円滑にする効果があります。

◇ほめ方の4タイプ
ほめ方には次の4タイプがありますが、どのほめ方が適切か、相手や状況を見て判断しましょう。
⑴相対評価
他人と比較した上での評価。「〇〇さんより上手ですね」
※近くに〇〇さんがいたら大変です!!
⑵結果評価
出ている結果に対する評価。「また売上がトップですね」
⑶絶対評価
努力の過程を評価。他との比較ではなく本人の成果を評価。「今度の企画すごく斬新ですね」
※感動を込めて言いましょう。
⑷プロセス評価
「〇〇さんのがんばりが認められましたね」
- ⑴相対評価よりも⑶絶対評価のほうが、純粋にすごいと思っているという印象を与えるため、ほめの効果が大きい。
- ⑵結果評価よりも⑷プロセス評価のほうが、いつも気にかけられている気がするため、よりうれしく感じられる。
- なお、⑵結果評価や⑷プロセス評価のほうが、ほめられた側の自信アップにつながりやすい。
◇5つのお世辞テクニック
お世辞のテクニック(1)ハッキリとほめる
「〇〇さんみたいにデキる先パイと仕事ができてうれしいです!」
お世辞は自分が価値ある存在だと思わせてくれる自己高揚動機 を満たしてくれるので、 たとえ見え透いたものであってもハッキリお世辞を言われると、その相手に好意をもつようになる。
お世辞のテクニック(2)誇張してほめる
「プロの料理よりおいしいよ!」
ほめるときは多少の誇張も必要。たとえば、単に「さすがですね」 ではなく、「ギネス級ですね」「表彰ものですね」などというくらいのほうが、 相手には伝わりやすい。
※「さすがですね」は使わない方が無難です。
お世辞のテクニック(3)何度もほめる
「○○さんてセンスいいですよね」「その時計おしゃれ!」「良い車ですね~」
お世辞に限らず、相手に印象づけたいことは何度も言ったほうが効果的。
繰り返しほめることで、相手もだんだんその気になる。すると、ほめるほうもさらに
心を込めてほめるようになる。
お世辞のテクニック(4)質問しながらほめる
「お義母さんの作る芋の煮っ転がし、おいしいですね!どうやって作るんですか?」
目上の人をほめるなら「何かを教えてもらいながらほめること」が効果的。さりげなく質問にほめ言葉をまぜるとよい。
お世辞のテクニック(5)相手のこだわりをほめる
「あなたらしいユニークな企画ね」「これはあなただからできたんだわ」
ファッションにあまり興味がない人の服装をほめるなど、相手が関心をもっていない
ことをほめても伝わりにくい。
「このアイデアは、写真に詳しい○○さんならではですね」など、好みや趣味などを事前に調べて、その部分をほめると効果的。
参考文献
『マンガでわかる ホンネを見抜く心理学』(精神科医 ゆうきゆう監修)西東社
『面白いほどよくわかる!他人の心理』(渋谷昌三)西東社
その他 私の経験と記憶から
よろしかったら、下記の記事もお読みくださるとうれしいです。
|
|
ポチッとしていただけるとうれしいです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d561270.1dc35f48.1d561271.7c645afd/?me_id=1229231&item_id=10000065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Forigotou%2Fhyalodeeppatch%2F2018renewal%2Fsarch_hyalodeep01_sp.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)