「絶対損する」とわかっているのに、ついやり続けてしまう…。
「人間は一度決めたことは、 損をしてもやり続ける」
という行動原理があります。これを「一貫性の原理」といいます。
タバコ、お酒、ギャンブル、暴飲暴食、宝くじ、夜更かし…。
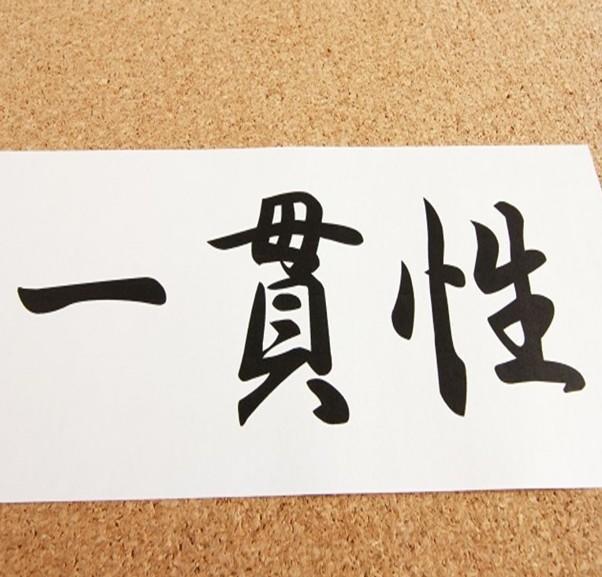
【行動の心理】「一貫性の原理」引き返すことの難しさ
「引き返す勇気」
なぜ人は引き返せないのか?
登山の事故も「引き返せば無事だった」というのが多いです。
「引き返す勇気」と言います。
準備を重ねて、頑張ったことを途中でやめることは勇気が必要です。
「引き返す勇気」と途中挫折は違う
途中挫折は次のマイナス評価につながります。
- 周囲から「意志の弱い人間」と思われる
- 「考えがスグに変わる人間」と思われる
何より「自分の中で納得できない」。
そもそも、人は自分にとってのマイナス評価を嫌います。
たとえ苦痛なことを続けて損をしても、 高い評価を得たいと考えがちな生き物です。
「あの人、初志貫徹で頑張っているね」
という評価です。
途中でやめると、評価が台無しになるような錯覚に襲われるのですね。
「根性がない」「スグに気が変わる」といったマイナス評価を想像してしまうのです。
この自分を高く評価したいと思う心理は「自己高揚欲求」 と呼ばれます。
人は褒められた後は気分が良くなります。これのことです。
頑張った分、周囲から評価されたいのは誰もが持つ欲求ですよね。
例えば他人に親切にする行動心理にしても、結果的に自分の得を考えてのものと言われます。
ということは、人間の行動は根本的に利得最大の原理に基づいていることになります。
冷静にそんな分析をすると、ちょっと寂しい気持ちになりますが、無償の親切だって世の中には少なからず存在するとは思います。
自己中心的行動と他者中心的行動
他者からの評価を重要視して行動するのは「他者中心的発想(他者チュー)」ですね。
「自己中心的発想(自己チュー)」の反対です。
自己チューは嫌われますが、「他者チュー」の人は始めよくても、だんだん生きるのが辛くなってくるでしょう。
他人の評価に依存するから、たくさんの人たちの考えに振り回されます。
多くの顔色も見なければならず、これは大変疲れますね。
「他者チュー」の傾向が強い人は、時には自己チューになる自分も必要だと思います。
また、個人の範囲でなく、社会や会社規模でも「わかっているのにやめられない」ことがあります。
あるプロジェクトを始めて、途中で「これは採算が合わない」と判明してもスグにやめることができないこと。
夢の超音速旅客機「コンコルド」の失敗が有名ですよね。
続けても採算が取れないとわかっているのに、
「ここでやめたら、これまでの努力が無駄になる」
として引き返すことができない状態にハマってましたよね。
運動競技で「この種目は自分に合わない」とわかっていても方向転換できないということもあります。
「せっかく何年も頑張ってきたのに…。ここでやめたらもったいない」
という意識から、才能を見出せないものにしがみつく心理もそれに該当するでしょう。
ただ、「石の上にも三年」という言葉もあります。
教育的見地から考えると、そこの判断は大変難しいところです。
「下手でもいいから続けることに意義がある」
という考えも決して間違いではないからです。
続けることは大変ですが、やめることも大きな勇気が必要です。
この秋、日本ハムの斎藤佑樹選手がついに引退しました。
引退を決意するまで、様々な心理的逡巡があったことは想像に難くありません。
スポンサーリンク
自己矛盾の不快感
タバコをやめたい⇒やめられない=「一貫性」ナシ
行動の一貫性を自覚すると、人は自己矛盾に苦しみます。
これを「認知的不協和」といいます。

不協和を解消しないと自分が苦しくて仕方がない。
そこで、自己矛盾を解消するために人が取る行動は次のとおりです。
1.行動を変える
現実的な方向転換です。これができたら自己矛盾は解消されます。
「タバコは害だ」⇒「やめよう」⇒本当にやめた
これで「一貫性」は保たれます。
でも、これがやめられなかった場合はやむなく次の手段に走ります。
2.認知を変える
タバコをやめることができない場合。
「一貫性」のない行動を正当化するために認識自体を変えようとします。
- 「世の中のすべての喫煙者が肺がんになっているわけじゃないから」
- 「喫煙者にも長生きしている人がいるから」
などと、自分に言い聞かせて行動を何とか正当化しようとします。
以前の私がそうでした。
古い話ですが、「長生き双子の金さん銀さん。喫煙家だった銀さんのほうが長生きした」
と公言してました。
3.自分の行動を評価し直す
タバコをやめることができない場合。
自分の喫煙行動に対する評価を変えることで正当化を図ろうとします。
具体的には 、
- 「自分はヘビースモーカーではないから、 発がん率は低いはず」
- 「ニコチン量の少ない銘柄のタバコに変えたから…」
- 「電子タバコは大丈夫」
といった言い訳を自分の中に作り出します。
このように、喫煙行動ひとつをとっても、 多くの要素が複雑に絡み合っていることがわかります。
- 「良いことはすぐやりなさい」
- 「良くないと思うことはすぐやめなさい」
言うのは簡単ですが、実行に移すのは難しいことです。
まとめると、
- 良いこと ⇒ 即実行
- 良くないこと ⇒ 即中止、または方向転換
⇒ができなければ「自己矛盾」に苦しみます。
さて、しかし、
「一貫性」を重要視するあまり、 自分に大きなストレスをかけてしまっているパターン
これが最も苦しいことかもしれませんね。
真面目な人によくありがちなパターンですね。
大きなストレスは自己嫌悪に繋がる場合があります。
これが最も厄介ですね。
「できない自分を認めてあげる」のは一貫性よりもある意味大切なのかもしれません。
スポンサーリンク
\メンタルケアの決定版アプリ/
【Awarefy】Googleベストアプリ受賞 ![]()
ポチッと応援していただけるとハッピーです!