高等学校の漢文の教科書によく出てくる「黔之驢」。
感情のままに激怒して不幸を招いた驢馬のお話しです。
まさに「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」の反対の行動…。
この話から得られる教訓は、現代の社会生活でも参考になることでしょう。
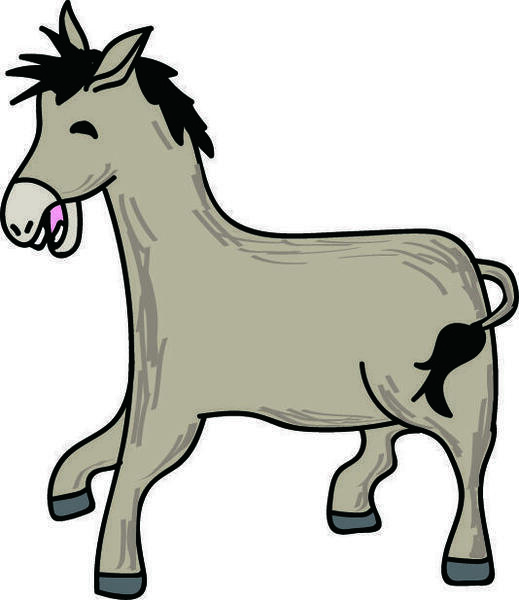
「学校の勉強は社会で役に立たない」としたり顔で言う人が多くいます。
「本当にそうかな?」と思います。
数学は論理的思考を鍛える訓練になります。
足し算と引き算だけできれば生活できるとは思いません。特にこれからは。
また、実学にこだわりすぎると、物事の本質は見えにくくなるような気がします。
漢文から得られる知恵も、見えないところで役に立つと思うのです。
【中国古典に学ぶ】「黔之驢」
【黔之驢】(柳宗元)黔州の驢馬〈訳文〉
黔州には驢馬(ろば)がいなかった。
物好きな人がいて、船に乗せて連れて来た。
連れては来たが、使い道がないので、山のふもとに放した。
虎が驢馬を見た。大変大きく見えた。
「神か」と思い、林の中に隠れて様子をうかがっていた。
そのうちに少しずつ近づいて、用心深く見たが相手のことがよくわからない。
ある日、驢馬が一声鳴いた。
虎は大変驚き、遠くに逃げた。
「自分に噛みつこうとしているのだ」と思って、ひどく恐れた。
しかし、近づいたり離れたりしながら観察してみると、特殊な能力はなさそうに思える。
その鳴き声にもますます慣れて、前や後ろに近づいてみたが、つかみかかることはしなかった。
だんだん近づいて、ますます慣れてくると、体をこすりつけるようになった。
驢馬はそれに我慢できず、虎を蹴飛ばした。
すると、虎は喜んで、「技はこれだけだな」と考えて、跳びかかり、大声でほえて、驢馬の喉を食いちぎり、肉を食い尽くして去った。

ああ、形の大きなものは徳があるように見え、声の大きなものは能力があるように見えるものだなあ。
あの時、技を出さなかったら、虎が獰猛とはいえども、最後まで疑いおそれて襲いかかることはなかったであろう。
今こうなってしまった。悲しいことだなあ。
【黔之驢】(柳宗元)ストーリーの要点整理
- 虎がはじめて驢馬を見て、体の大きさに驚く
- 虎は驢馬のことがわからない
- 驢馬の鳴き声を聞いて虎はさらに怖がる
- 驢馬を何回も見ているうちに虎はだんだん慣れてくる
- 虎がますます慣れて驢馬に体をすり寄せる
- 虎をウザいと思った驢馬は怒って蹴る
- 虎は驢馬の技が蹴ることだけだと知り、安心して驢馬に襲いかかる
- 特技を見せたために身を滅ぼしたことを嘆く(作者)
スポンサーリンク
【黔之驢】人はどう生きるべきか
【黔之驢】驢馬はなぜ虎に食われてしまったか
- 虎は、自分の安全を考え、慎重に驢馬の力量を測ろうとした
- 驢馬は、虎を見ても何も考えずマイペースを貫いた
何が良くないかというと、驢馬は、
- 自分の力量を理解していない
- 虎の力量の観察を怠った
驢馬の最大の失敗
- 自分が弱いことを、軽率な行動によって敵に教えてしまったこと
人間も、自分の本性をむやみにさらけ出すのは危険ですね。
ある程度、自分をオブラートに包んでおいたほうが安全といえます。
【黔之驢】怒るときも上手な演出が必要
また、むやみやたらと怒るのも得策ではありません。
いざという時に怒る方が効果的なのは言うまでもありませんね。
いつも怒ってばかりいると、「また怒っている」と呆れられてしまいます。
よい刀は、ふだんは鞘(さや)に収まっているもの。
常に刀を抜いていては、ナマクラ刀といって切れ味がなくなります。
驢馬も最後まで刀を抜くべきではありませんでした。
必要だったのは、我慢すること、それからさりげなく逃げることでした。
【安全に生き抜くために】驢馬はどうすべきだったか
- 虎が自分よりも強いことを最初に自覚するべきだった
- 虎が自分を恐れていることに気が付くべきだった
- 強いふりをしながら、少しずつ虎から距離をおくべきだった
ところで、熊と出会った時、背中を向けて逃げるのは最悪の逃げ方と言われています。
目をそらさず少しずつ後ずさりをする、そして距離を置くのが正しいらしいです。
相当な精神力が必要でしょうけど…。
他に、傘を持っていたら静かに広げるのが良いと聞いたことがあります。
自分を大きく見せる効果があるらしいです。
また、煙草の煙をくゆらせるのも効果があると聞いたことがあります。
事実かどうかわかりませんが、頭上に広がる煙が自分を大きく見せる効果につながり、熊は警戒心を抱くらしいです。
ということから考えると、虎は驢馬を怖がっているわけですから、その心理状態を利用するべきでした。
ゆったりとした様子を見せ、「強いかもしれない」という虚像を抱かせたまま、少しずつ距離を取り、虎がいない場所に避難するべきだった、、、と私は妄想します。
【熱帯魚】孤弱なグローライトテトラは賢かった
中学時代飼っていた熱帯魚の保身術
中学校時代、私は熱帯魚を飼育していました。
種類ごちゃまぜの水槽でした。
その中には、小型シクリッド科の気性の激しい魚もいました。
カラシン科の中心にいたのは、ネオンテトラでした。
彼らは、小柄で弱い魚です。常に10匹以上の群れを作って泳いでいました。
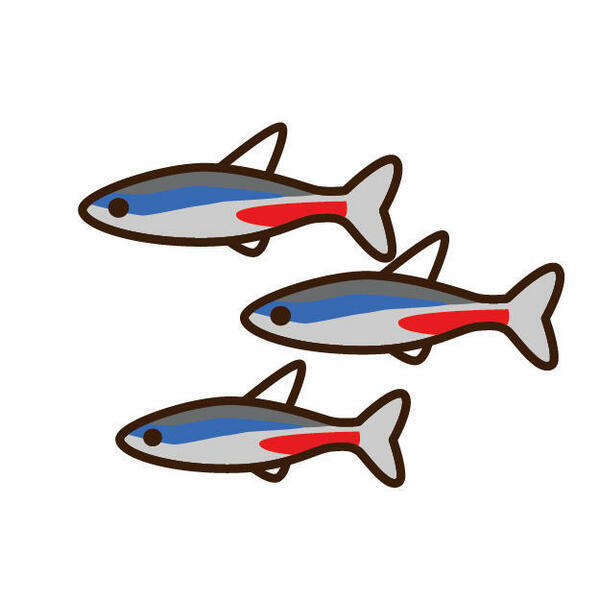
その水槽に、グローライトテトラを1匹だけ買って入れたのです。(かわいそうなことをしました。お金がなかったもので…。当時は今より高額でした)
不安だったに違いありません。
彼はすぐさま、ネオンテトラの群れの最後尾にくっついて一緒に行動するようになりました。
同じカラシン科で、サイズも近いので安心感があったのだと思います。
さすがにかわいそうになり、数週間後、5~6匹のグローライトテトラを買ってきて水槽に入れました。
すると、彼は、ネオンテトラの群れから離れ、グローライトテトラの群れに合流するようになりました。
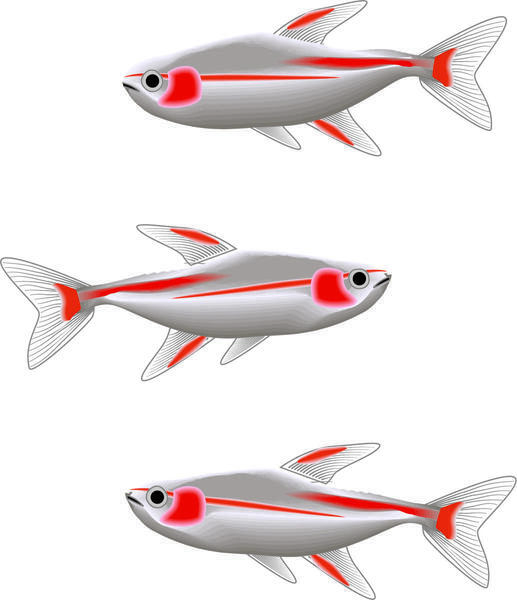
小さな熱帯魚でさえ、生き抜くために異なる種の群れに入っていたわけです。
生きるための本能でしょうね。
見習うべき点があります。
一番良くないのは驢馬を運んだ人
結局、連れてきた驢馬を山の麓に放した人が一番良くないですね。
無責任な行動です。まるで今の大人…!?。
北海道でも、アライグマが野生化して大変困ったことになっています。
自分勝手な人が、未来の子ども達に負の遺産を置き残しているわけです。
ダメですね。
少しでも良い未来を後の世代に残す努力をしていかなければ…。
追記
昨夜、北陸で大地震がありました。皆さまのご無事をお祈りいたします。
数人の友人が北陸に住んでいます。LINEしようか迷いましたが、通信混乱で迷惑を掛けることを恐れて静観していました。
23時頃になり、友人からLINEの連絡が届き、ひとまず安堵しました。
地震の1回目は震度2、3程度でしたが、2回目が震度5で3Mの津波が来るとの警報があり、近くの小学校に避難した次第。幸い、津波の影響は全くと言っていいほどではありませんでしたが、これから本番が来そうで怖いです。東南海地震の前兆かもしれません。
昨年10~12月に南太平洋バヌアツ諸島、パプアニューギニア、インドネシア、フィリピンでM7.0以上の地震が発生しています。
近いうち、同じことフィリピン以北で起こるだろうとは思っていました。(東日本大震災の前、ニュージーランドで大地震があったのはご記憶か?)。今回の地震を東南海地震の前兆と捉え、国を挙げてできる限りの備えをしておくべきと考えます。
冷静な長文から、まずは落ち着いているようです。
365日で最もゆったり過ごしたい元旦の災害に心が傷みます。
微力ながら、私にできる支援はしたいと考えております。
★過去記事もどうぞごひいきにwww.happy-power-up.com
ポチッと応援していただけるとハッピーです!

